|
����̗��ŖK�ꂽ���́@�����[�S�X�����B�A�A�M�Z�J���̂����̎O�����X�����F�j�A�A�N���A�`�A�A�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�ł���B
�������C�ݐ��A�����̋�Ǎ]�ɕC�G�A���₻��ȏ�Ƃ���������ȂǂŁA�ŋߐl�C�����܂��Ă���n��ł���B
�������Ɍi�F�͔����������B�����������I���čł�����Ȉ�ۂ����̂̓{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i�ł������B�@�@
�����N�O�܂Ŏ��͂����̍��ɂ��āA�w��ǒm��Ȃ������B
�m���Ă����̂̓`�g�[�Ƃ����哝�̂��������ƁA�������Y���ł͂��邪�\�A�Ƃ͈�����Љ��`���ł��邱�ƁA��s���x�I�O���[�h�ł��邱�Ƃ��炢�B
���̃��[�S�œ��킪�N�����ĉ������댯���A�Ƃ������Ƃ̓j���[�X�Œm���Ă������A�ƂĂ����G�����ł낭�ɐV�����ǂ�ł��Ȃ������B
10�N���炢�O�Ɂ@����f������ĊS�������A��x�s���Ă݂������Ƃ͂Ȃ��Ă������`�����X���Ȃ������B
2005�N�Ɂ@��w���邱�Ƃ̉��x�p���X�`�i�E�Z���r�A�I�s��@�Ƃ����{��ǂ݁@�s�������C���������܂����B�����[�S�ɍs�����ƂɌ��߂����N���炢�O����A�J���`���[�Z���^�[�Ŋ֘A�̍u�����Ƃ�����A�{��ǂ肵�n�߂��B
���[�S�X�����B�A(���[�S�Ə������Ƃɂ���)��́A�Ƃ����̂Ń��[�S�Ƃ������͂����Ɨ��j�I�ɑ��݂��Ă����Ǝv������ł������A���������Ƃɂ������[�S�͂�����70�N�]��̗��j���������Ă��Ȃ��B�@
���������̍l���Ɋ�Â��A1918�N�A��X�����̒P�ꖯ�����ƂƂ��Ắ@�Z���r�A�l�A�N���A�`�A�l�A�X�����F�j�A�l���������@���[�S�X�����B�A�����ƍ������ς��̂́A29�N�ł���B
|
�����Ł@�C�ɂȂ�̂́A�{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i�Ƃ��������o�Ă��Ȃ����Ƃł���B
������F���w�o���J���@���[�S�̔ߌ��x�ł́A
�{�X�j�A�ɏZ�ރC�X�������k�́@�Ǝ��̖����Ƃ��Ă̈������Ă��Ȃ������B
(���̗��R�Ƃ���)���̃��[�c�����ǂ�A���Ƃ��ƃZ���r�A�l���N���A�`�A�l�ł��邪�@�g���R�x�z�̊ԂɁA�����Ƃ��Ă̋A���ӎ���w��ǎ����A�C�X�������k�ł��邱�ƂɎ���̃A�C�f���e�B�e�B�[�����o���Ă����B(�{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i�j�Ƃ́@�Ⴄ�Ƃ��낪����)
�Љ��`�̐��̂��Ƃł́A�M���A�C�f���e�B�e�B�[�Ƃ��閯���̑��݂͋�����Ȃ������B������1961�N�ɂȂ��āA�Ǝ��̖����Ƃ��Ă̒n�ʂ��F�߂���悤�ɂȂ�A���X�����l�Ƃ��������J�e�S���[���������ꂽ�B
�E�E�E�Ƃ���B
|
���j�̐��Ȃ̂ŁA�����̂��������ʼn�̂��Ă��܂����Ƃ������Ă����������͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
��̗̂��R�͂��������̐��藧���̒��ɂ������B���[�S�X�����B�A�Ƃ������낤�Ƃ����Ƃ��A�Z���r�A�ƃN���A�`�A�ł͍\�z������Ă����B�Z���r�A�̓Z���r�A�哱�̒����W�����Ƃ��߂����A�N���A�`�A�͘A�M��O��Ƃ��郆�[�S�X�����v�z�������Ă����B�����͂��Ƃ��Ɗ낤�����̂������̂��B
1945�N�ɂ́@�@�����p�~�B�@
���[�S�X�����B�A�A�M�l�����a������������`�g�[�哝�̂̂��ƁA�Ǝ��̎Љ��`�̓�������A80�N�@�`�g�[�̎��ɂ��A�@���S�͂��������B�@
�e���a���̌����̕������l���I�ɑ����Z���r�A�l�̌����̏k�����Ӗ����邱�ƁA�e���a���̌o�ϊi���ȂǁA���Ƃ��ƕ��������Ă�����肪�\�ʉ��A�o�ϕs���@�B���������Ƃ��ɁA�@�����v�����N�����B
�X�����F�j�A�ł��N���A�`�A�ł����Y�}��}�ƍق̔p�~�A�������}�������������B�������āA�A�M����̗��E�ւƓ����B
�@
91�N�X�����F�j�A�ƃN���A�`�A�́@�Ɨ��錾�B�X�����F�j�A�̗��E�́@�\���Ԑ푈�ŏI��������A�@�����ɃZ���r�A�l�������Z�ށ@�N���A�`�A�ł́@���������킪�J��L����ꂽ(�s�������Ł@���҈ꖜ�l�A���\�Z���l)��92�N2��27���@����I���錾�B
�ŏI�I�ɂ͓��X�����H�j�A�n��������98�N�ɏI���B
�N���A�`�A�̗��j���T�ς��Ă��邤���ɁA�O���S�[�������̂��Ƃ��v���o�����B����Ƃ����͍̂ł����̖����̖������鏊�Ȃ��������̂ł���B�����O���̌��t�͕������x�̈Ⴂ�����Ȃ��Ƃ����B�����Ł@���̌����\�킷�����ւ̂�����肪�@�����A�C�f���e�B�e�B�[�̏؍��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����̂��B���e����g�p�����ۂ������ɂ܂ł�����邱�Ƃ́@���������̓n�v�X�u���O�Ƃɂ��݂��܂�����͂Ȃ��@���Ƃ̈ӎv�\���Ȃ̂ł��낤�B���������̂��Ƃ͋t�ɁA���̃N���A�`�A�ӎ����������A�ߋ��̂ق�̈ꎞ���́@�L���̓y�������Ă��������ւ̉�A�Ƃ����@��N���A�`�A��`�̏ł�����̂ł͂Ȃ����B(����͎��̑S���l�I�Ȋ��z�A�����ɂ��Ă�����肷����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ������͂����Ɍf����{�̂ǂ����ŁA�ǂ�)
��N���A�`�A��`����Z���r�A��`�ƂƂ��ɑ��풆��90�N��̓���ł̔�l���I�ȍs�ׂ������炷�����̌����̈�ɂȂ����ƌ����Ă���B
�{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i��92�N�A�@�Z�����[�ɂ��Ɨ�������A�d�b����������F�����B(�{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i��P�Ƀ{�X�j�A�Ə���)
�������O�����̏Z�ށA�{�X�j�A�ł́A�@�N���A�`�A�l�Z���r�A�l�́@�����̂��Ȃ��ɖ{���������Ă���B�{�X�j�A�E�C�X�������k�͖{���������ʎ㏬�����B�@�{�X�j�A���܂������̕���ɂȂ��Ă��Ȃ������@91�N3���A���łɃ~���V�F���B�b�`�ƃg�D�W�}���́A�{�X�j�A���Z���r�A�A�N���A�`�A�ŕ������邱�Ƃɓ��ӂ��Ă����Ƃ��`������B(�ȏ�A��Ɂ@�w�o���J�����[�S�̔ߌ��x���Q�l�ɂ���)
�@�����ł́@�������e����@�W�c���C�v�Ƃ����������܂����s�ׂ܂Ő����鎖�Ԃ��N�������B
�@���R�Ƃ��āA�@�w�o���J���j�x�@�Ő�O��(�R��o�Ŏ�)�ł�
�@�T�A�@������`�I�ȁ@�����Ƃɂ��
�@�U�A�@�}�X���f�B�A�ɂ�閯����`�v���p�K���_
�@�V�A�@���[�S���O�̖�����`�O���[�v�̉e��
�@�W�A�@���������𐳋`�Ƃ��鍑�ې��_
�@���������O�G�v���ɉ����āA�@������̌Z��E���̋L���A�@�ߐe�����A�@�S�l���h�q�ɂ��ʏ�p�̕��킪�e�n�ɂ�����Ă��ē��肪�p�ӂ��������Ɓ@���@�������Ă���B�@
95�N�Ɂ@�{�X�j�A�A�M(�{�X�j�A�E���X�����ƃN���A�`�A�l)�ƃZ���r�A���a���Ƃ�����̐��̂���Ȃ�P��̍��ƁA�Ƃ����`���Ƃ邱�Ƃɂ���ďI�����݂��B
�N���A�`�A�ł��{�X�j�A�ł�����̌_�@�ƂȂ����@�Z���r�A�l���@�́@���܂���������Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B
�T���G�{�̂ǂ��܂ł����������V������W�̘A�Ȃ�́@���̋L����������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B
�ǂ{
���@�K�C�h�u�b�N�@
�� �n���̕�����
�� �N���A�`�A�@�����l�u�b�N�X
���@�@���j�@
�o���J��������K���ƁA�Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��H�Ƃ����^�₪�N����B���������߂āA��ɓ�����̂����ꂱ��ǂ�ł݂��B�܂�����͂Ȃ��̂��{�ɂ���ĈႢ������A������܂Ƃ߂邱�Ƃ́A���ۏ�ɑa�����ɂƂ��Ď�ɗ]���Ƃ������B
���ǁ@�w�n���̕������x�̊e�����̍Ō�ɕt�����Ă���A���j����ԊȒP�ŗv�̂悭�܂Ƃ܂��Ă����B
�� �}���@�o���J���̗��j�@�Ő�O�@���@�͏o���[�V��
�� �o���J���j�@�Ő�O�@�ҁ@�R��o�Ŏ��@98�N
���@�r�U���c�Ɠ����E���V�A�@�@�X���B��@�@�u�k�Ё@�r�W���A���Ő��E�̗��j�@85�N
���@�r�U���c�ƃX�����@�@���_��^�I����ҕv���@�������_�Ё@���E�̗��j�P�P�@98�N
�� �o���J���@���[�S�ߌ��̐[�w�@������F���@���{�o�ϐV�����@93�N
�@�@�J���`���[�Z���^�[�Ł@�����搶�̍u������u�����B�@���̎��̃e�L�X�g�����̖{
�@�@���G�ȁ@����j��������₷��������Ă��邪�A�@�o�ŔN�������̂ŁA���̌�̐i�W�ɂӂ���Ă��Ȃ��̂��c�O�@
���@�L���X�g���j�@�V�@�X���B�璘�@�R��o�ŎЁ@
���@�w���[�}���c�ƃi�`�X�x�@�@���V���Y���@�@���t�V��
�@�@�@�e���j
�@���@�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�j�@���o�[�g�E�i�E�h�[�j���A�W�����E�u�E�`�E�t�@�C�����@�P�����@95�N(94�N)
�� �N���A�`�A�@�@�W�����W���E�J�X�e�����A�K�u���G���E���B�_�����@�����Ё@���ɃN�Z�W��
�A���҂ɂ���Č������������A�T���Ƃ��鎑�����Ⴄ�̂����l���قȂ����肷����̂��������B�{�S�~���h�ɂ��ĂȂǂ́A�t�@�C���̐����V�����A�Ŏ��͂Ƃ肢��Ă����邪�A95�N�ȑO�̖{�ł͎�������Ă��Ȃ��B(�Q�l�̂��߂ɂ������ɂ��Ắ@�o�ŔN�x(�|����̂ɂ��Ắ@�����̔��s�N��)�������Y����)
���������킯�ŁA���̗����L�̋L�q�������̖����͂���Ǝv���B�@�S�̂�����̕��́@���ꂼ��̖{�ɂ������Ă���������Ǝv���܂��B
�����@�@�ǂݕ�
�@�@���@�w���邱�Ƃ̉��@�p���X�e�B�i�E�Z���r�A�I�s�x�@�l���c���F���@��i��
�@�@�@���@�w�o���J���̖S�삽���x�@�J�v����
�@�@���@�w�Ō�̓w�́x�@�ق��@���[�}�l�̕���@���쎵�����@�V����
�@�� �@ �w�J�[���̃Q�[���x�@�S�[�h���E�X�e�B�[�����Y���@�����n����
|
�`�������A�Ƃ����W�������ɂȂ�̂��H����������ŋꂵ�߂��Ă���l�̕`�ʂ͒P�Ȃ�G���^���Ƃ͈�����悵�Ă���悤�Ɏv���B
1994�N�A�@�{�X�j�A�́@�}���K�C(�T���G�{���k�ɂ��钬)�ɏZ�ރJ�[���Ƃ��������̘b�B���̒��͐V�s�X�Ƌ��s�X����Ɋu�Ă��Ă���B���̓Z���r�A�R�ɕ�͂���Ă��āA�H�Ƃ̔z�����͐V�s�X�B�J�[���������s�X�̏Z���͋���n��Ȃ�������Ȃ����A�g���B���Ƃ���̂Ȃ�����n��l�X���Z���r�A�R�̃X�i�C�p�[�͑_���Ă���B���������̒��A�J�[���͉p���r�`�r�����̕��m�������A�t�ɔޏ������b�ɂȂ�B���������ǃJ�[���͎q�����v�������B
���������Z���r�A�R�̖C�������A�s����̃��[���ɂ̂��߂�ނ��Ƃ�����Ȃ��B
�����́@�{�X�j�A�����̂Ă��̂��H�@
�r�`�r�����̌��t�u���ɍ��A�����݂̓��E�����̂Ă��Ƃ��A�N�͐����������~���鉽�����蒆�ɂ����߂Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������|�����鉽������ɓ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�������āA�ޏ��͔ޏ��̃Q�[�������邽�߂Ɂ@�e�����X�g�ɂȂ�B
�ޏ����e�����X�g�ɂȂ炴��Ȃ�������͂���Ă���̕`�ʂ́A�����������Ƃ������{�X�j�A�ŁA�ӂ��ɋN�����Ă����̂��낤�Ǝv�킹������̂ŁA�������߂�����悤�Ȏv���œǂB
���������͍����p���X�e�B�i�Ȃǂł������Ă���̂��낤�B�@
�{�X�j�A�E�w���c�F�S�r�i�𗷍s���A�@���x�ƂȂ��A���̏������v���Ԃ��Ă����B
|
�����@���̑�
�@�@�@���@�w�s�s�̒n���C�x�@�@�w���G�M�@�m�s�s�o��
�f���@
�@�w�T���G�{�̉ԁx�@�@�����12�N�������T���G���H(�f��̃^�C�g���́@�{�@�ɂȂ��Ă���)�̕ꖺ�̘b�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꂵ�������̒��ʼn��Ƃ����ƍK���ɐ����悤�Ɗ撣���̉ߋ����C�w���s��p�̂��Ƃ���A�I��ɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�w�G�l�~�[���C���x�@�����ɂ��A�����J�f�悾����ǁA�@���펞�̘b�Ȃ̂ł����Ă���
�@
������
�@����͏��Ȃ������B
 |
 |
 |
| �y���_���g�g�b�v |
|
�|�[�`(����������) |
 |
 |
 |
| �u���b�h�Ŕ������V�g�̂��l�` |
�C�� |
�h�J�̂�����ƃJ�[�h |
 |
 |
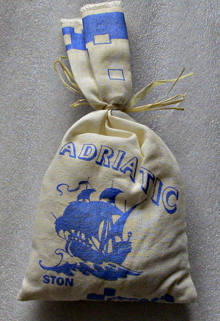 |
���F�Q�^(��X�[�v�̑f�炵�����A�@
�����������̂Ńn�[�u�\���g�Ƃ��Ďg���Ă��� |
�s�����̉� |
�X�g���̉� |
 |
 |
 |
| �`���R���[�g |
�`���R���[�g |
���x���_�[�@�@�I�C���Ɠ����� |
 |
 |
 |
| �t�����P�����C�� |
|
|
|