10�N�ȏ�O�����o���g�O�J���ɂ͂����ƍs�������Ƃ������Ă������A����͍ŏ��ɂ��������悤�ɏ\���R�̂��ƂƁA����f��Ɏ䂩��Ă̂��ƂŁA���ۂ̌i�F�⒬�̗l�q���ʐ^�Ɍ�������A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������B
�s���O�ɃK�C�h�u�b�N�̎ʐ^�Ȃǂ�����i���v�������ׂ邱�Ƃ͂ł������A����قǔ������Ƃ��낾�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B
�G�߂��悩�����B���̂��������ł̓��C���b�N�̉Ԑ���B�����ȓ�ɏZ�ސl�ԂɂƂ��ă��C���b�N�͒������Ȃ̂ő労���B
���@���F�@�Ԏ��@�̏������Ԃ��~���`�ɂт�����܂��č炢�Ă��ĂƂĂ��₩�B
�x�O�ɏo��ƁA�X�Ƒ����A�ꏊ�ɂ���Ă͈�ʂ̍̉Ԕ��Ɣ����сB���������̏Z��ł���Ƃ���ł͖w�ǂ݂Ȃ����A���{�̂��傫�������������肵�Ă���悤���B
�������Ď�s�̋��s�X�@�����̖ʉe���c���Ă��Ă��������������̂��y���������B���Ƀ^�����̓����w���`�b�N�������B
�܂��C������̂��D���Ȏ��ɂƂ��ẮA�T�[���}�[���⃀�t���ł݂��C���Y����Ȃ��B
�������i�F�̊��\�ł��邢�����������B
�O�J���̂����A���@�G�X�g�j�A�A���g���B�A�́@�h�C�c�l�i���A�h�C�c�R�m�c�ɂ���č��̂��Ƃ�z���ꂽ�Ƃ����Ă悢���ł���B
�L���X�g���z���͂ɂ���čs���@�c�s�A�Ȃ�肩���ʼn��@���������Ƃ��@�w�k�̏\���R�x�ɏ�����Ă����̂ŁA�h�C�c�l�̍��ՁA���݂����A�܂����n�l�̓h�C�c�l���ǂ��݂Ă���̂��낤���A�Ƃ����^��_���������B���A���̒��ł͒��O�̃\���B�G�g�x�z�ւ̉��l�̕����������낤�ȁA�Ɨ\�z���Ă����B
�������A���n�̐l�i�Ƃ����Ă��K�C�h�������Ȃ����j�ɕ����`�����X�͂Ȃ������B�@�X���[�K�C�h�ňꏏ�ɒ����o�X�ɏ�����肷��Ƃ��낢�뎿������Ă���邱�Ƃ���̂����B
���߂āA�s���O�ɂ͂��������ɂ����ǂ�ł��Ȃ������@�o���g�O���̗��j�@�̋ߑ�ȍ~�̂Ƃ����ǂނƁA���̃h�C�c�l�����͋R�m�c�����U���Ă������ƌ��͎҂ł��葱���A���n���͔_�z��Ԃɂ�����Ă������Ƃ�������Ă����B
�����A�_���ւ̋���A�܂��̂̎w���������̂��h�C�c�l�q�t�����ł���A���ꂪ�����^���̌��Ƃ��Ȃ����i���̂Ƃ��͊��ɐV���ɂȂ��Ă���̂ŁA���[�e���h�q�t�A�Ӓn�̈�������������@�����L���X�g���͐Z�����Ă���̂ŁA�͂ł����ĉ��@�����܂�K�v�͂Ȃ��@�Ђ�����A����̂���������Ă���悩�����̂ˁA�Ƃ������邪�j
�܂��_�z����ɂ���ĉ�����ꂽ�_�������͓y�n�������Ȃ��������ߓs�s�֗��ꂽ�B���傤�ǎY�Ɗv���̎����������̂ŁA�����S���J���͂ƂȂ�A�\���B�G�g���ł́i�o���J�������ȂǂƂ���ׂāj�H�Ɖ��̐i�n��ƂȂ��Ă���B�i�_�z����̎��A�����y�n����ɂ���邱�Ƃ��ł������g�A�j�A�ł́@�_���͔_���ɂƂǂ܂����B���̃��g�A�j�A�͎Y�Ƃ̋ߑ㉻�ɂ�������Ƃ����j
�N���������Ƃ̈����Ƃ��Ă݂�����ł��邪�A�������j������ƈꌾ�ł͌����Ȃ����̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�Е��͂����Ȃ����̂��Ƃ��A�Ȃǂƌ����͖̂`���ł��낤�B
�ǂ{
�K�C�h�u�b�N�@�@�F�@�n���̕������w�o���g�̍��X�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԁ@�o���g�O��
�I�s�@�@�@�@�@�@�F�@�o���g�O�����j�I�s�@�T�A�U�@�@�V�@�@���@�ā@���@�@�ʗ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�G�X�g�j�A�I�s�x�@���؍������@�V����
���j���@�@�@�@�@�@�F�@����@�o���g�O���̗��j�@�u�����q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���g�O���j�@��ؓO���@�@���C��w�o�ʼn�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�k�̏\���R�x�@�R���i���@���i�ґI�����`�G�i���݂͍u�k�Њw�p���ɂɂ͂����Ă���悤�ł��j
�G���T�����D���ڎw���������\���R�͗L�������A���[���b�p�k�����Ɍ����Ă̏\���R�����������Ƃ�m�����̂́@���[���b�p�L���X�g���j�̍u������u����悤�ɂȂ��Ă���̂��ƁB
�\���R�̓G���T������ڎw�����R���_�l�W�Ȃ��̑�s�E���J��L�����킯�����A�k���\���R�ɂ����Ă��c�s�ȎE�C���s�����Ƃ����B
���������́w�k�̏\���R�x�@�ɂ�
�u�ً��k��������͈����ɂ���ăL���X�g���M�ւƋ������邱�Ƃ́A���@�I�ł͂Ȃ��v�A�Ƃ͂����茾�������i���̂������Ƃ�������Ă���B
���̎c�s�Ȉً��k�����ɑ��āi����l�̗����ł͓��R�Ȃ̂����j�u����͊Ԉ���Ă���v�Ƃ��̃R���X�^���c�̏@����c�ŕ��\�����|�[�����h�i�����������ƂɎ��͂������芴�����Ă��܂����B�@
�R���X�^���c�̏@����c�͎O�l���̋��c���o�����Ƃɑ����Ƃ��ĊJ���ꂽ���̂����A�����Łu�ً��k��������͈����ɂ���ăL���X�g���k�ւƋ������邱�Ƃ͍��@�I�ł͂Ȃ��v�Ǝ咣�����l������̂͂��������Ƃ��B
�ْ[�̍߂Ń{�w�~�A�̃t�X�͕��Y�ɏ������A���ɖS���Ȃ��Ă����E�C�N���t�͕��������Ĉ�̂��Ă��ꂽ�i�Ă���Ă��܂��Ǝ���̕��������肦�Ȃ����߁j�A������������c�ɂ����Ăł���B |
:
���p�W�@�@�F�w�u���̕����v�ւ̗��x�@���r���q���@�������_�V��
���w�@�@�@�@�F�w�l���x�@�@�\�t�B.�I�N�T�l�����@ ���쏑�[�@�G�X�g�j�A�_���̑�ꎟ���O����Ɨ�����܂ł̘b
�f���@�@�@�@�F�u�p���E�^�f�E�V�������v�A�_���E�~�c�L�G���B�b�`�̏����������Ƃɂ����A���W�F�C�E���C�_�ē�i
�@�@�@�@�@�@�@�@19���I���߂́@�|�[�����h�i�����g�A�j�A�j�̔_��������
�@�@�@�@�@�@�@�@���~�I�ƃW�����G�b�g�̂悤�ɁA���̈�����̉Ƃ̎�҂̗��������Ɍ����s��ȊG�����B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�����̓��V�A�x�z���ɂ���A�i�R���Ă����i�|���I���ɖ]���������ʂ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ߑ��ŗx������̂�����̑�͂��Ⴌ�i���ꂪ���C�_��i�H�Ƃ��������Ƃ�������������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�f��̍ŏ��ƍŌ�A�S����̃p���őr���̂悤�ȍ������𒅂��l�X��O�ɂ��Ă̎��̘N�ǂ���ۓI������
�@�@�@�@�@�@�@�@�|�[�����h�A���g�A�j�A�̓����̏�m���ɂ��Q�l�ɂȂ�
�@�@�@�@�@�@�F�u�N�����b�T���Œ��H���v�W�����k�E�����[�v�X�̎剉�Ƃ����đ�l�C�Ȃ悤�ł��邪�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�ē̃C���}���E���[�O�́@�G�X�g�j�A�̃T�[���}�[���o�g
�@�@�@�@�@�@�@�@�W�����k�E�����[������V�w�l������Ă���Ɛ��w���G�X�g�j�A�l�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�G�X�g�j�A�ɂ��Ă͂��܂�ӂ���Ă��Ȃ����A�p���ɂ̓G�X�g�j�A��������Ƃ����̂�����炵���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�p���͌|�p�ƂɂƂ��ē���̒��ł���܂��i�`�X��\�A�̎x�z����̂���Ă���l�̒��ł����������Ƃ��@������
�@�@�@�@�@�@�@�@���݃p���ɏZ�ރG�X�g�j�A�l��1000�l���炢���������B
���͊ςĂ��Ȃ����@�~���[�W�J���Ł@SEMPO�@�Ƃ��������琤�������f���ɂ������̂�����B
�Ƃ����
1940�N7�������ꃖ���A�����琤�������̃��_���l�̂��߂Ƀr�U�s���邱�ƂɂȂ������A
�Ƃ������̉����Ƃ���1939�N�C�M���X�̃o���t�H�A�錾�P��������Ƃ����b���A�p���X�`�i�ɂ��Ă̍u�����Ă��Ē������B
�C�M���X�͂���܂ŁA���R�͂Ƃ����ꃆ�_���l�̃i�V���i���E�z�[����Ƃ����l���Ń��_���l���x���Ă����B
����������ŁA���_���l�̓i�`�X�h�C�c�ɔ��Q����Ă���̂Ńh�C�c�ɂ����Ƃ͐�ɂȂ����A�A���u���ɂ͔��p����Ђ낪���Ă���B�����ŃA���u���h�C�c�ɂ������ρA�Ƃ����킯���B
�������o���t�H�A�錾��P�����A���Q����Ă��郆�_���l���C�M���X�ɂ̂���Ă���p�C�v������Ă��܂����B
�B��̓��������V�x���A����A�E���W�I�X�g�b�N�A�։�A�_�˂��o�R���ē������{�Ɏx�z���ɂ�������C�֓n�邱���������̂��������B��C����Ȃ�A�A�����J�ł��C�X���G���ɂł��s�����Ƃ��o�����̂��B
�����������R�Ń��_���l�����̓J�E�i�X�̓��{�l�̎��قɎE�������̂������ŁA�ނ�̂��߂ɂ��肬�萙�����͉w�z�[���ł܂ł����������������̂ł��B |
����������
�����Ă����e�[�u���N���X�̏�ɕ��ׂĂ݂܂����B�ǂ�������Ȃ��̂ł͂���܂���B
���������@�傫�����Ă݂��
 |
 |
| �W���j�p�[�i�m���j�ō��ꂽ�w����@�o�^�[�i�C�t |
�o���g�C�́@���߂̎Y�n
 |
 |
 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| �}�O�l�b�g |
���g���B�A�A���[�K�̎s��Ŕ���������
����͓�����ł����B�X���[�N����Ă���悤�ŁA
���������i��K�v���Ȃ������ł��B |
|
 |
 |
�V�g�l�`�i���@�J�[���[�N���[�^�[�̂��Ŕ��������[�X�҂�
�E�@���B���j���X�Ŕ������f�p�Ȗؒ���j |
���́@���ˑ|���l�A�@�E�́@�o�C�L���O |
 |
 |
�E���̃s�A�X�A�@�{���A�O�p�̎D�̂悤�Ȃ��͎̂w�ւɂ����܂��B�@�������̎����O�������͂����Ă����̂������ł��B
�@���ꂼ��@�E�Ɏ������悤�ɍK�^�������炷�Ӗ�����������Ƃ����B�B |
 |
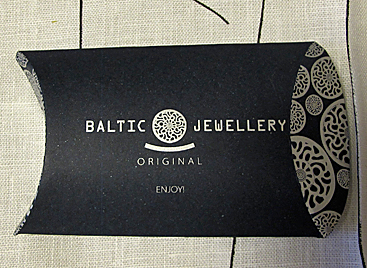 |
| |
�P�[�X�̃f�U�C�����f�G�A������ƃP���g���ۂ� |
 |
 |
| �����ߑ��̃X�J�[�g���́@�~���N���� |
����݂Ƃ����X�q |
 |
 |
| ���g���B�A�̐Ό��ƃo�X�\���g |
���ꂩ��A����m��Ȃ����̂��߂ɗ��s���t������Ă��������������ԁB,�厖�ȑ厖�ȋL�O�̕i�B
�悢�����ԂƓY�������̂������Ŏv���o�[�����ƂȂ������Ƃ��@�ƂĂ��������v���Ă��܂��B2013�D09.28�@��
|