|
�����̗��ł������Ȃ̂����A�@����͎��n�������A�Ƃ��������ƐS�c��̕���������B
�ŋ߂̎��̗��s�̓��[���b�p�̒�����A���ߓ��̌Ñ��Ղ�K�˂闷����ł���B�@����Ύ��Ԃ�k�闷���B�@�������A����K�ꂽ�x�������́@���̓�������̌����Ă������ł���B��Ɉ�l�ŖK�˂��x���i�E�A�[�X�͏d���S�Ɏc�����B
�|�c�_��������̐�㏈���ɂ��Ẳ�k���s�Ȃ�ꂽ�ꏊ���B�@
�ӂ��E��Ȃǂ��܂�C�ɂ����Ȃ��̂����A�܂��Ɍ���j�̌�����s�����łƂĂ��h���I�������B
�c�O�������͔̂��p�ق̎��Ԃ��Z���������ƁB�@�ł��Z���Ȃ�����A�C�ɂȂ��Ă����G���݂邱�Ƃ͏o�����B
���s�O�E��ɓǂ{�Ɗς��f��
���f�肷��܂ł��Ȃ����Ƃł����A���܂����̎�ɂ�����A�ς邱�Ƃ��ł����͈͓��ŁA����́A�Ƃ����������̂��������ɂ����܂���B
�@
�Q�l��
�w�_�����[�}�鍑�x�@�e�r�ǐ��@�u�k�АV��
�@�@�_�����[�}�鍑�A�@���j�ɖ��邭�Ȃ���A�@�h�C�c�̂��Ƃ��Ƃ͋C�����Ȃ���������Ȃ��B�@�����_���Ȃ̂��A�������[�}�I�Ȃ̂��𖾂炩�ɂ��ׂ��A9���I�̃J�[����邩��1806�N�̒鍑�ŖS�܂ł̃h�C�c�̗��j���@�c���`�@�`���ł��ǂ�B
�@
�w����@�h�C�c�̗��j�x�����ޖ�@�����V��
�@���N���O�ɁA���̍u���������Ƃ�����A��i�ʼn��������Ȑa�m�Ƃ������e�A�ł���N�͉s�������B�@���{�ɂ͐��ԗl�͂����Ă��Љ�͂Ȃ��A�Ƃ��A�@���摜�ɂ��Ă̘b�A�ȂǂƂĂ��V�N�ł������̂ŁA�������������������߂ēǂ��A����́@���s�O�ɂ�����ēǂB�@
�@���w����C���@�̎{�݂ʼn߂������o���������A�Љ�j�A�Ƃ���������J�����������ɁA�O�f�̏����A�c��Ƃ����A����Η��j�I�l��ʂ��ď�����Ă���̂ƑΏƓI�Ɂ@�i���������j������A�c�邽���̓����A�����ɂ��Ă��q�ׂ��Ă��邪�j�_���A�s���̐�����ӎ����ǂ��ł��������A�@�����v�Ȃǂɂ������̃y�[�W����₳��Ă���B�܂��A���ݏo�҂��J���҂̑��������ɂȂ��Ă��邪�A����ƃA�W�[�����Ɋւ��邱�Ƃɂ܂Ō��y����Ă���B
�w�h�C�c�l�̐S�x�@�����`�l�@��g�V��
�h�C�c�l�ƃ������R���[�Ƃ̊W�ɂ��āA���̕��y�I�v���Ƃ��ăh�C�c�̐[���X�̂��Ƃ�������Ă���B
�@�i���C�}���ɂ���Q�[�e�̃K���e���n�E�X�̉����X�������j
���_���l�W
�w�h�C�c�ƃ��_���l�x�@��Y�@�u�k�АV��
�w�h�C�c�ɂ����郆�_���l�̗��j�x�@���[�I�E�Y�B�[���F���X�@����J��������
�@�I���ꐢ�I���납��@�h�C�c�ɂ̓��_���l���Z��ł����B�@1096�N�̑���\���R�܂ł́A�@�@���̈Ⴂ�A�������炭��A�H������K���̈Ⴂ�ɂ�������炸�A�@�h�C�c�l�Ƌ������������Ă����B�@�\���R�̏]�R�҂����̓��_��������P�����@�A���Ă���̂�S�ĂƂ肠���A�@�t�炤���͎̂E�Q�����B
���̎����烆�_���l�̋��̗��j���n�܂�B
�����Q�b�g�[�ɕ����߁A��N�Ɍ����ł���l���܂Ō��߂�ꂽ�i�l���𑝂₳�Ȃ��悤�A�������A�l���͑����q����Ԃ͋ɂ߂Ĉ��������j
�������A�@���ɏ��ƁA���Ղ̍˂ɏG�ł��A���_���l�́@����M���Ȃǂɏd�p����A����ꂽ����ł͂��������A�x�������킦�Ă������B���̉ߒ��ł́A����������Ă�������ĕԂ��Ȃ���Γ��ݓ|���A�A�Q�b�g�[���Ă������ɂ���A�y�X�g�ȂǗ��s��ƑS�ă��_���l�̂����ɂ���B
�����������Q�̗��j��ǂނƃq�g���[���ˑR�ψٓI�Ɍ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂��A�Ǝv���Ă���B
�h�C�c���Y�p�̍��A�Ȋw�̍��A�����I�ŗD�ꂽ���]�̎�����̂��鍑�ł��锽�ʁA�i�`�̑䓪�������悤�Ȗ��m�֖��Ŗ����{�Ȑl�Ԃ̏W�c�Ƃ����v���Ȃ��悤�ȂƂ��낪����B���̂Ȃ̂��B��q�̈����ޖ玁�⍂���`�l���̖{�Ƃ��֘A���邪�A�����Ƃ�������l���Ă݂����B
�w�h�C�c���j�̗��x�@���h���Y�@�����I��
�w��Ȃ��n�x�@���ꉳ�F�@���o�Ŏ�
�@���̓���͓��h�C�c����̗��s�L
�w�h�C�c�@�Ós�ƌÏ�Ɛ����x���Z���ǁ@�R��o�ŎЁ@���E���j�̗�
�h�C�c�̗��j�ɂ��āA�܂��q�ׂĂ���A���̗��j��H��悤�ɒ�������A�K�C�h�u�b�N�ł͂��邪�A�z�e�����ȂǂƂ����̂ł͂Ȃ����j���S�̃K�C�h�i�h�C�c�ɂ��Ă̊�{�I�m���邽�߂ɂ́A�n���̕������A�Ƃ���Ɠ������悢�Ƃ����C������j�@
�ǂݕ�
�w����������A�������X�p�C�x�@�W�����E���E�J��
�x�������̕ǁA�Ƃ����Ǝv���o���̂����̏����B�s���O�ɂقڎl�\�N�Ԃ�ɓǂݕԂ������A�X�p�C�̔߈���������Ă��āA�@���݂Ȃ��������́@���E�J���̌���̈���Ɖ��߂Ďv�����B
�w����x�������x�@�W���[�t�E�L���m��
�|�c�_����k�����̃x������������A�f�扻���ꂽ���A�@�����̕����f�R�ʔ����B
�������ꂽ�x������������ŁA�z�e���E�A�h������A�|�c�_���̃c�B�c�F�[���G���z�t�{�a�̑O�̌@���o�Ă���̂ŁA���s�̊y���݂��������B�������ꏊ�̊y���݂����œǂނ悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�h�C�c�l�̓��]�������Ă̓����̋삯�����Ȃǎ��ɖʔ����B
�w�x�������̏H�x�@�t�]���
������킩��Ǖ���܂ł̎�ɓ��h�C�c������B�@
��҂͂��ƊO�����ŁA�@�����̂��Ƃ������̂ɏ����d���Ăɂ����A�Ƃ��Ƃ����ł����Ă���B�@��������ڂ����������Ȃ̂ŁA�����̐���������킩��B�@
�����ǂ�Ń��C�v�c�B�q�̃j�R���C����@�̂��Ƃ�m��A���̒��̃o�b�n�䂩��̃g�[�}�X������A�j�R���C����̕����݂����Ȃ����B
�w���C�}���̃��b�e�x�@�g�[�}�X�E�}���@��g����
�w�Ⴋ�E�F���e���̔Y�݁x�̔ߗ��̑���̃V�������b�e�E�P�X�g�i�[�����Ə��Ԏg�����āA���C�}���̃G���t�@���g���قɂ���Ă���B�����֎��X�Ɨ��q�A���X�Ƃ�����ׂ���n�߂�B�i���������ƁA�\���N�O�ɓr���܂œǂ�ŁA����̗��s�̂��߂ɂ܂��ǂݎn�߂����A�܂��ǂ݂�����Ă��Ȃ��̂ł���ȏ㏑���悤���Ȃ����A���̂�����ׂ肩��Q�[�e�̎p�������яオ�邱�ƂɂȂ��Ă���j
�K�C�h�u�b�N
�n���̕������͂������A�@
�w�x�������A�h���X�f���x�@�����l�u�b�N�X�@���o�a�o���
�ς��f��
���̃h�C�c��m�邽�߂̈�̂Ă��ĂƂ���
�w���o���̋F���x
�@�~�����w���̏��q�吶�]�t�B�[���Z�̒��Ԃ����ƁA��\�͂Ńi�`�ɒ�R�A�u�œ|�q�b�g���[�v�̃r���܂��������B�ǐS�ɏ]���l����ς��Ȃ��������߂Ɏ��Y�ɂ��ꂽ���b�̉f�扻�B�@
�M����Ƃ���ɏ}����Ƃ����������́A������Ɛ^���̂ł��Ȃ����ƂƑ��h���邪�A������f��ɂ܂ł����Ă�A�i����ɑi������̂ɂ���j�Ƃ����̂����ɂ͂Ђ�������B
�J���`���[�̃��_���̗��j�u���̐搶�ɂ��̂��Ƃ�b������A��͂�A�f�扻�ɂ̓J�g���b�N����̋����ӎu�������Ă����������B����Ɗ֘A���邪�A�w���߂Ĉꎞ�Ԃ����ł��x�@�y�[�^�[�E�V���i�C�_�[���@�@�Ƃ����{���ǂB���̖{�̑тɂ́@�i�`�X�������A�x�������̒n�����������ՓI���҂��Ƃ����A�A�A�ނ������̂́A�h�C�c�l�s�������̂����₩�ȗE�C�������@�Ƃ���B�A���l�E�t�����N���B��ƂŐ����ł����̂�������l��������������A�Ƃ������ƒN�ł��͒m���Ă��邪�A�œ_�͉������ȃA���l�ŁA���͎҂ł͂Ȃ������B���ꂪ�ς�����A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ����A�ǂ����C�ɂȂ�B
�w����x�������x�@�{�̂Ƃ���łӂꂽ�B�w��O�̒j�x��w�J�T�u�����J�x���ӎ����č�����Ƃ������Ƃ��ȂقǂƎv�킹��悤�Ȃ���B
�w�x�������A�V�g�̎��x
�V�g�������I�[�o�[�𒅂����N�̒j�A�Ő폟�L�O��̏�ň�x�݂��Ă���A�Ƃ�����ʂ��܂��A��ۓI�B�@�X�g�[���[�̂��Ƃ͂����Ă����Ƃ��ā@�ǂ̂��鎞���̃x������������ŁA�ǂ��ǂ��Ȃ��Ă���̂����ǂ�������̂������B
�w�P���l�̂��߂̃\�i�^�x�@
�����Ƃ̐l�X�͓���O�͎��R�͂Ȃ��Ă��d���͂��������A���͎��Ǝ҂����ɑ����B���̂��������Ǝ�����������ޕ������łĂ��Ă���B����ɑ��āA���Ǝ���̎��R��D��ꂽ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����v���ō�����f�悾�������B
�V���^�[�W�̋Lj����A�Ď��Ώێ҂̐������Ɏ䂩��Ă����̂����A�@�w�̂܂������̂т��A�V���^�[�W�̃��B�[�X���[-��т���ۓI�B���X�g�������B
���s���A�V���^�[�W�ł������͐����c��A�c���ɂȂ����肵�Ă��邪�A������l�͐�Ɍ��I�Ȏd���ɂ͏A���Ȃ��A�ƃK�C�h�������Ă������A������Ȃ�قǂƎv�킹����V�[�����������B
���̃��B�[�X���[��т��������o�D�E�����b�q�E�~���[�G�����ŖS���Ȃ������Ƃ𗷍s���O�̃j���[�X�Œm�����B
���y�Y
���ߓ��̂悤�ɒ��������̂͂���܂���B�@���{�ł�������悤�Ȃ��̂���B�U�C�t�F���̂��l�`���N���X�}�X�߂��Ȃ�ƁA�f�p�[�g�Ŕ����Ă���B
|

|

|
|
�}�C�Z���̃J�b�v
(�l�b�g�ŒT���ƌ��n�Ɠ����ʂ̂��l�i�Ŕ�����悤�ł��B�@���ꕨ��������{�ŁA�Ƃ����l�������邩������Ȃ����A
�i�������łȂ������v���o���悷���Ƃ��Ȃ�̂ŁA�����܂���) |
|

|

|
| �U�C�t�F���̉��o���l�`�@����23�p |
�U�C�t�F���̋���Ɛ��̑��@����15�Z���` |
|

|

|
| �U�C�t�F���Ŕ������N���X�}�X�p���i�v�L�� |
|

|

|
| �A���y���}���O�b�Y���낢��@�ʂ������ |
�}�E�X�p�b�h |
|

|

|
| �}�O�l�b�g |
�}�X�R�b�g |
|

|

|
|
����͕Б����́q�i�߁r�ŁA�����Б���
�Ԃ́q�~�܂�r�A�h�A�ɂ����āA
�����Ă������A�Ƃ�����Ȃ��ŁA�̍��}�ɂ���B |
�@�G�R�o�b�O |
|
���ɂ����݂₰�ɂ����B���R�A�����Ԃ́A�h���g�E�f�B�X�^�[�u�ɂ���̂��Ǝv������A�u�z�e���ŁA�����Е��͉��Ə����Ă��邩�m���Ă���H�n�E�X�N���[�j���O�E�v���[�Y��v�B�������āA�����ɂ��ďo�����Ă���B |
|

|
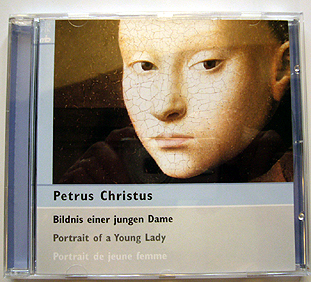
|
| �h���X�f���̐��\���ˋ���̐��̑��̂b�c |
�x�������A�G��ق̃N���X�g�D�X�̊G�̉���b�c |
 |
 |
| �N���X�}�X�I�[�i�����g |
�s���[�^�[���̏���i�U�C�t�F���͂��Ǝ��̎Y�n�j |
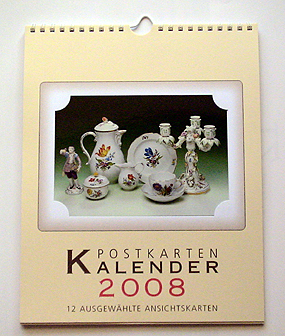 |
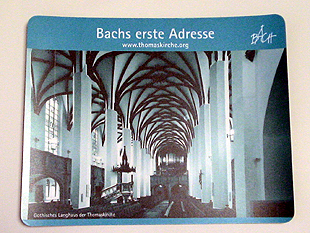 |
|
�}�C�Z���̃J�����_�[ |
���C�v�j�b�c�̃j�R���C����̃}�E�X�p�b�h |
|
�@
�@
����͂��y�Y�ł͂Ȃ���
��`���̖ƐœX�Ń��C���Ȃǂ̉t�̕����ƁA���̑܂ɂ���ĕ������ē��{�̒����܂ŊJ���Ȃ��悤�ɂƌ����ēn�����B
|
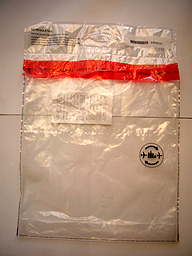 |
|
�ƐœX�̉t�̕�������� |
�@
|