|
4時半 起床 衣類などの詰め替えに時間がかかってしまった。
6時45分 朝食 今日もオムレツを焼いてもらった。
ユーロが少なくなったのでホテルで1万円ばかり両替した。 レートが悪い。 今かなり円高傾向の筈なのに 1ユーロ176円についた。
(あとでカードの請求書をみて分かったことだが、昨日の列車の切符は160円/ユーロで計算されていた)
7時45分 出発
8時30分 エアフルトのドーム広場着
 |
|
ドーム広場 |
ローマ教皇よりゲルマニア布教の委任をうけていた聖ボニファティウスが、742年にここに司教区をつくることの承認をもとめ、752年に教会堂をつくったのが、このドームの始まり。
まだ時間がはやすぎて、教会が開いていなので、 まず街歩き。
ドーム広場を出てすぐのところ。
20世紀初頭、ドイツが一番お金のあったころに流行った家が建っていた。
中はレンガだが外は石を張っている。人の顔の家、新しいがルネッサンス様式。
昔の教会で,今は閉めてあるところもある。
今は教会税を払っているのは30パーセントくらいだそうだ。
 |

|
| 万聖教会(13から14世紀) |
塔だけが残っているものも多い(セント・ポール教会) |
万聖教会通りには、下の ウインドミューレ(風車)と名づけられた16世紀に建てられて 19世紀に建てなおされ、珍しいことに東独時代に修復された建物で現在は音楽学校 (殆どの建物の修復は統一後西側のお金でなされている) がある。
|

|

|
|
拡大すると、1982年87年に
修復されたことが分かります |
倉庫街 。 〈秤通り〉といわれて、昔大きな秤があって関税を徴収していた場所。
|

|

|
|
ヴァーゲ・ガッセ(秤小路)
上の飾りはそれにちなむものかどうか分からない |
中世のままの細い道 |
旧市街は古い綺麗な町並み。 建物は中世から近代までさまざまだが、道は中世のままだそうだ。
本当の中世の建物というのは教会くらいで、殆どは19世紀の建物だそうだ。
本当の中世の町は歩けないそうだ。 暗い、汚い、臭い、危ない から。
19世紀のドイツ人が中世を作り変えた、と現地のガイドさんは言っていた。以前、阿部謹也氏のお話でも、そう話されていたことを思い出した。
エアフルトという街は『大青』というアブラナ科の植物からとれる青の染料で富を築いた街。 大青はエアフルトに年間三トンの金をもたらしたという。(インド航路発見でインディゴ がもたらされて廃れた)
その当時の富の証とも言うべき大きな家々が立ち並んでいる。
|

|

|
| シュテルンベルグの家 |
ギュルデン・シュテルン |
この青の染料で染められた布製品や陶器がこの町の特産ということで買いたかったが、何分にも
朝がはやすぎてお店が開いていなかった。ここに来たよい記念になると思うのにとても残念。
下左写真は、東独時代の終わりごろに造られた建物。この時期になると建物も町並みにあわせるようになってきた。
|

|

|
|
スペースの関係で、この場所にはりつけたが、
これはクレーマー橋の土手をあがってきたところあたり
|
9時 アウグスティヌス会修道院
ここはルターが1505年から11年まで滞在したところなので、来てみたかったが、中心部から少し離れている (といっても10分も歩いてない) ので、あきらめていた。
現地ガイドが「皆さん、まだ疲れていないでしょうから」と案内してくださって 嬉しかった。
|

|

|
|
|
|

|

|
|
|
|
この修道院は13世紀半ば頃建てられた。
既にゴシック建築の時代なので、石造天井を造る技術はあったが、
質素を旨とするため、天井は木製である。
ルターはここで<自己聖化はできない、秘蹟も善行も救済のための浄めにはならない>ことを体験を通してしって、義認説をたてるに至り、カトリックとは異なる立場をとることになったのだ。
ルターの時代は男子修道院だったが、現在は女子修道院。
といっても修道女は6,7人しかいないそうだ。 |
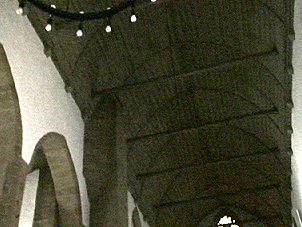
|
修道院を出て、
別のところでまたゲラ川をわたる。
エアフルトの名前の由来は、中世、ゲラはエラ、フルトは浅瀬という意味で、 エアフルトはゲラ川の
浅瀬にできた町、ということになる。 (フルトはほかにもフランクフルトなどがある)
川に面白い飾りがあった
|

|
|
ゲラ川 流れで小さな水車が回るらしい |
そうして、有名なクレーマー橋へ。
エアフルトは 交通の要衝の地であった。
この橋はなんと フランスのパリからウクライナのキエフにまで通じていた、通称 ヴィア・レギム(王の道) のルートに架かっている橋だという。 (ヨーロッパの国々は地続きだということを再認識)
島国に住む日本人には、こんな昔に、幾つもの国を越えて、徒歩や馬で旅をする、ということは驚きだ。もっとも一人の商人が全行程を旅する、ということはあまりなかったのかもしれないが。
また、ハンザ都市のリューベックからニュルンベルグに至るルート上にもエアフルトの町はある。
東西・南北の主要幹線の交差点にある町なのだ。
|

|
|
クレーマー橋 |
橋の上は、商店街で橋の上とは思えない。
お店は入れ替わりも多いそうだ。 マイセン磁器やザイフェンの木製人形のお店もあった。
カフェもある。
|

|

|
|
これでも橋の上 |
橋をほぼ渡ったところで、川辺におりる。反対側から橋を見る。
ここが丁度浅瀬で昔はここを渡ったがそのうち木製の橋ができて何度か消失した後1325年石橋になった、ということだった。
|

|

|
|
道が水に沈んでいるところが浅瀬で
昔、人や牛馬が渡ったところ |
市庁舎橋からの眺め
(拡大するとシナゴーグの場所が分かる) |
橋を別方向から眺めたり市庁舎橋(ラートハウスブリュッケ)から眺めたり。 写真ストップ。
橋の上で「右手にシナゴーグがあります」、といわれた。
エアフルトは商業で栄えた町なのでユダヤ人も多くいたのだろう。
やはり水辺は気持ちがいい。時間が早いからなのか 他に観光客もいない。
もっとゆっくりマイペースで歩いてみたい町だ。そうしてまた街の中心に戻る。
フィッシュマルクト広場
16世紀に建てられ ルネッサンス様式の建物が広場を囲む。
左写真は大青の商人のギルドホール(今はレストラン)
右写真は1562年にルネサンス様式で建てられた商人の館、ローテン・オクセン
|

|

|
| もと ギルドホール |
ローテン・オクセン(赤い牡牛が) |
中央には市の自由、特権を示す象徴のローラント像が立っている。(1591年)
ローラントとはカール大帝(9世紀前後)に仕えた、騎士ローラン(叙事詩、『ローランの歌』に出てくる)に由来。14世紀になってドイツ各地で都市の力の象徴としてマルクト広場に建てられるようになったもの。手にする裁きの剣は、独自の裁判権の象徴。
市庁舎に入る、
お店のワッペンを集めて展示してあるのが面白かった。
ライオンとプレッツエルがパン屋、 入れ歯や鍛冶屋など、何屋さんかなかなか当てられない。
|

|

|
|
ローラント像(拡大するとはっきりします) |
|
この町はボニファティウスによって礎が築かれたということで、ホールにボニファティウスがゲルマン
の部族を改宗させている図がある、とガイドブックに出ていたが、そこは見なかった。
見たのは二階のルターがらみの絵
市内観光が終わったところで、またドーム広場に戻る。途中パッヘルベルがオルガニストだったというプレディガー教会の横を通った。
|

|

|
|
プレディガー教会 |
ドーム広場へ戻ってきて大聖堂へ。
ところがここは「中では説明できないから、適当にみてください。 ステンドグラス(14世紀)が素晴らしくてマリア様もいろいろありますよ」とガイド氏は言う。この教会は78段の階段の上にある。バスは広場の向こう。お手洗いはまだその先の地下。 それなのに、添乗員は「教会をみて15分後にバスに集合してください」。 と教会の前で解散。
教会内は正味5分くらいしかいられない計算。 おまけにバスの中ではヴォルフラムの燭台という有名な彫刻作品があります、と言っておきながらその場所も教えない。ともかく走まわっても何処に何があるか分からないので受け付けの人に聞いて(英語が通じる。きちんとした英語でなくても、ヴォルフラム、といえば通じるし、その他みたいものは制作年などをノートに書いておいて、みせられるように準備をしていった)、その場所に連れて行ってもらって写真だけは撮る。
母たちに、階段の途中の売店で絵葉書とパンフレットを買うように頼んでおいたので少し時間は助かったが、あわただしくて、私の好きな古い彫刻などじっくり見るひまもなかった。
一角獣とマドンナの祭壇画は入ったすぐのところにあった。
|

|
|
|

|
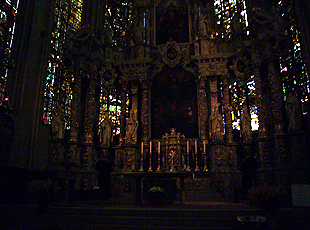
|
|
正面の祭壇 |
|

|

|
| 燭台 ヴァルフラム像(1160年ごろの作) |
聖クリストファーの壁画 下は
グライヘン伯の墓石(1270年ごろ)
|
|

|

|
|
1150年ごろのエアフルトのマドンナ像 |
|
|

|

|
|
側廊と身廊の高さが同じで
ハレンキルヘ型だということがよく分かる |
いそいでいたが、入ってすぐに気がついたのは、とても広々とした感じがすること。今回の旅行でこれまでいくつかみたと同じハレンキルヘという形のつくりだ。どうもこのあたりはこのタイプの教会が多いようだ。
側廊が身廊と同じ高さなので広い感じがするのだ。 特にこの教会は側廊の幅が広いので、まるで体育館に入ったようだった。
日本に帰って パンフレットをみると、この教会には回廊もちゃんとある。 私は回廊が好きなのに見なかった。
それにしてもどうしてこう急がせるのか。 次のレストランの予約の時間があるのかもしれないがもう少し余裕をもって予定を組んでほしかった。さすが、このときはあとで添乗員が 私の時間の読み違えですみませんでした、とは言っていたが。
サン・セヴェリ教会が大聖堂の前に建っていて、それも見ることになっていたが、修復中、ということで見られなかった。 ガイドブックには、ここは〈ドイツ随一といわれる美しいハレンキルヘで、貴重な美術作品がちりばめてある〉と書かれていたので、ぜひともみたかった。とても残念。
エアフルトは一人で歩き回るのに手ごろなサイズ。徒歩で充分観光できる。
古い道筋が残っていて、川もありとてもステキな町。ここに泊ってもいいのではないかと思った。
バスの中でも現地ガイド氏は
「エアフルトには世界遺産がないことが泣き所だが、いい町ですよ。 11月の末からはドイツの他の町と同じようにドーム広場でクリスマスマーケットが開かれます。 クリスマスマーケットをめぐるツアーでよく一日に三つも回るツアーがあるがどこへいっても同じで、違うのはマグカップだけ。 一つの所をじっくり見るといいです。この町でも大聖堂がライトアップされてきれいですよ」と言っていた。
このエアフルトと次のアイゼナハを案内してくださったガイド氏はとてもよく歴史など知っていて良かった。(推測だが、ガイドには、ガイドという仕事をするために土地の歴史や文化を勉強した人と、歴史や文化を知っているからガイドになった人がいるのではないか。このO氏は後者だと思う)
そのⅡへ
|