|
朝食 7時 初めてアメリカンの朝食 また中庭でとるというのも気持ちがいい。 (上着がないとちょっとひんやり)
中庭のラベンダーがみごとだった。かなり丈が高い。
朝食後少し散歩。
|

|

|
| 泊まったホテル、ロワ・ルネ |
イルカの噴水 |
エクスの町には噴水が多い。もともとこの地は温泉郷として知られ、紀元前124年、ローマのコンスル、セクスティウスがケルト人のアントルモンの砦を攻撃、破壊して、この温泉郷のそばに要塞陣地を建設、これをアクエア・セクスティアエ(セクスティウスの水)と呼んだ。 エクスの名はここからきている。丁度子供たちが学校へ行く時間。
噴水のところで待ち合わせしている子供もいた。
9時 出発 9時10分ごろ左手に、セザンヌの絵で有名なサン・ビクトワール山が見える。
|

|

|
| サン・ビクトワール山(よく見る絵とは角度が違う) |
左写真の拡大 頂上に十字架が立っている |
遠くに岩山を見ながら進む。
バスの中でのガイドのO氏の話。
去年オーストラリアで小麦が不作だったので、今年はフランスでも休耕地で小麦がつくられている。これからは、農業をやったほうが都会に出るより儲かる。
バルセロナが水不足なので、マルセイユから水船で水を運んでいる
チュートン人(ゲルマン民族の一部族)がローマを目指して進軍してきたのを紀元前102年、ローマの将軍マリウスが撃退。 それにあやかって、農家や漁師の家では子供によくマリウスという名をつける、などの話を聞いた。
10時15分〜11時45分 ル・トロネ修道院 着
|

|
| 入り口にあった案内図 |
建てられたのは 1160年〜1170年 最終的完成は 1190年。三姉妹のなかでは一番先に建てられたもの。つまり長女。
何年か前に
『粗い石』 ル・トロネ修道院工事監督の日記 プイヨン著 を読んで、なんとか行ってみたいと願っていた修道院である。
子供が校外学習に来ているのをやり過ごして中に入る。
先ず作業部屋。 ぶどう酒をつくるときに 炭酸ガスが出るのでそれを逃がすために壁に小さな穴もあいている。
|

|

|
| 作業部屋 |
圧搾器 |
それから回廊を通って、寝室に。
|

|
| 修道士の寝室 右手の階段から回廊の二階に出られる |
一人ずつの区画がきまっていて、わら布団を敷いて寝た。壁の厚さが窓を見るとよく分かる。
教会堂
回廊の二階へ行き、中庭を見下ろす。
|

|
| ル・トロネ修道院は森の中にある |
|

|

|
|
敷地に高低差がある。
奥の回廊の方が左手より高くなっていることが分かる。
|
泉水 |
おりて、チャプタールームを見る。
|

|
|
チャプタールーム |
|

|

|
|
隅に岩。もとからあったのだろうか |
|

|
|
|
 |

|
|
|
10時50分〜、11時40分、フリータイム
いつの間にか、小学生たちはいなくなって、殆ど我々だけがあちこちに散って思い思いに回廊で写真を撮ったり、佇んだり、また部屋に入ったりして、しばし僧院の静けさにひたる。
充分時間があるようだが、足りない。せめてあと一時間はぼんやりしていたかった。
|

|
この彫刻のまったくない、ただ円く刳り抜かれただけの規則的なアーチの美しさに圧倒された。
この角を曲がると回廊は一段高くなる。右がすでに高くなっている |
|

|
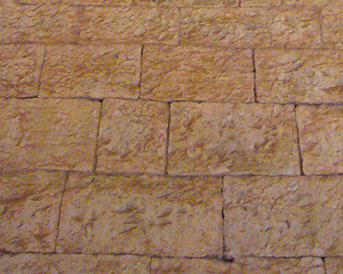
|
|
きっちり切り出して積まれた石壁、漆喰で間を埋めていない |
『粗い石』 という本の石積みの苦労について書かれたところを思い出す。
・・・・・(この地の石は)砕けやすく、不確かで、ひび割れの元になる筋や欠陥が一杯だ。層も怪しげで、神の怒りに触れたように即刻崩れてしまう・・・
立派な石を使いたがる石工、この土地で産する石で建てるほかない修道会の事情。石工と話し、事情を納得させ、鍛冶屋と協力して道具を作り石が切り出せるようになるまでの苦労。
さらに工事監督(勿論修道士)の考えは 外壁は空積み、といって、間に漆喰を使わずに積むやり方。 漆喰がないと、上下の重なりあう面を全く凸凹のないように平らに仕上げなければならない。上に次々と重みがかかってくるので、石が割れてしまうからだ。
そのところを思い出しながら、きっかり詰まれた石の壁を見る。
壁の表面の粗さは光の反射でレース模様のようにみえることをねらって、である。
外に出る。
泉水もある
|

|
|
泉 |
|

|
| 側面、本当に何も飾りがないので、アクセントにも塔(鐘楼)は必要だ |
|

|

|
鐘楼 ちょっとアンバランスに思える細さだが、
『粗い石』では ・・・・シトーでは宗規によって禁じられている。 高すぎる、もっと低くするか、なしにするよう・・・僧院長に言われて、単調で窓のない正面には、単純で頑丈なピラミッドはは必要、と・・・・・・・四角錐、四は三位一体の三角形が第四の位格とも言うべき聖母様を型取ることを示唆された、なで肩の細い優しい形、これは修道院を守ってくださる聖母マリア様のマントである・・・、と工事監督(修道士) は説明している。
帰ってきて、本を見ると近くに小川がある。『粗い石』 に川のことが何度も出てくる。もっと時間があれば周りもゆっくり見られたのに残念。この修道院では回廊が一番印象的だった。
シンプルで、が現代建築にも通ずるところがあると、建築家もよくここに来るそうだ。再び来ることはないと思うが、もう一度来て、ゆっくりしたい場所。
売店でちょっと買い物。 ここで、『粗い石』 のフランス語版を発見、写真が綺麗だった。 重いので買わなかったが、今とても後悔している。
9日目ー2へ
|